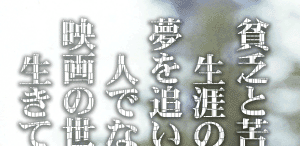 |
 |
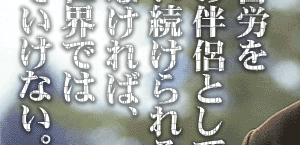 |
 |
 |
 |
Masato Kato 加藤 正人さん
脚本家
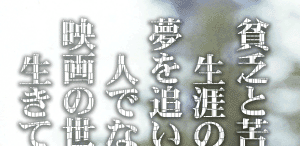 |
 |
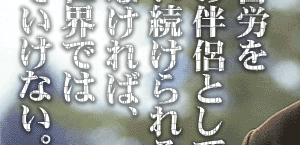 |
 |
 |
 |
|
脚本を書くことは、人間を描くこと。人の思いを描写すること。細やかな感情を丁寧に描けば、ドラマに綾が生まれていく。
|
|
人の思いを描写する |
|
(2003.3 Vol39 掲載)
|
 800/TWO LAP RUNNERS (1994年、アルゴピクチャーズ) 監督:広木隆一 脚本:加藤正人 出演:松岡俊介、野村祐人、 有村つぐみ、 袴田吉彦 ほか |
 三たびの海峡 (1995年、松竹) 監督:神山征二郎 脚本:神山征二郎、加藤正人 出演:三國連太郎、南野陽子、 風間杜夫、隆大介、 永島敏行 ほか |
 ゲレンデがとけるほど恋したい。 (1996年、東宝) 監督:広木隆一 脚本:加藤正人、宮島秀司 出演:清水美砂、大沢たかお、 西田尚美、 鈴木一真 ほか |
 女学生の友 (2001年、東宝) 監督:篠原哲雄 脚本:加藤正人 出演:山崎努、前田亜季、 野村佑香、山崎一、 毬谷友子 ほか |
 天国への階段 (2002年、日本テレビ) 演出:鶴橋康夫、岡本浩一 脚本:池端俊策、加藤正人 出演:佐藤浩市、本上まなみ、 加藤雅也、中村俊介、 古手川祐子 ほか |
|
 |
かとう・まさと |