

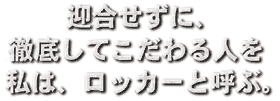
ロックの大音響とスタイルに魅せられてはじまったドラマー人生だったが、
多くの経験をして、ロックとは心の底に「魂」を
持ち続けている人の
「生き方の表現」であることに気がついた。


今、私は年上の人の生きざまを聴くことが非常に楽しい。秋田という限られた地域の中にも人知れず我が道を貫いているロッカーがいる。そういう人に出会うと、そこからまた点が広がり、すごい人を紹介される。人は人との交わりの中でしか出会う事ができないのだと秋田に住むようになってつくづく感じている。
自分にしかできないものを
生き方がロックな人物を紹介する『そんなおやじのロック魂』はFM秋田の一時間番組『J ユS SOUND BOX』のコーナー番組である。こういうプロデュースをしていると、今までメディアに登場したこともなかった人物をラジオの電波に乗せるという快感が味わえる。私のプロデュースの考え方は基本的に自分だけにしかできないものを創り出していくことである。これは、バンド活動で培われてきた習性のようなものだと思う。
ビートルズで音楽に目覚め、レッド・ツェッペリンでロックにのめりこんで以来、私の心を占領してきたロック。高校時代からバンド活動をはじめていろいろな仲間との出会いがあったが、やはりオフコースで培われたものが大きい。
まだガキだったあの頃
小田和正、鈴木康博のオフコースに二十二歳で加わり、売れ出したのは『愛を止めないで』『さよなら』以降の二十六歳ころだった。ロックの殿堂日本武道館でのコンサートも体験し、まさに上げ潮だった。しかし、今、思うと、あのころの自分はまだまだ「ガキ」だった。ロック、イコール破天荒な生き方をすることだ、などという考え方は高校時代と少しも変わっていなかった。
突っ走る日々が続いていた時、メンバーで四歳上の清水は二人きりになるとよく「お前なぁ、今はこれだけど、ほんまは一人なんやで。それをわかっておけよ、しっかりしいや」と口にした。どこか訳知りでおとなびていた清水は何かに気づいていたのだろうが、私は「また意味ありげなことを言って」位にしか思っていなかった。だが、今思うと彼の言う通りだった。
「自分のスティック一本で生きてみせる」という反発心を頼りに苦しいバンド活動を続けてきた私は七歳年上の小田や鈴木の目から見れば「やんちゃ坊主」だった。だが、「売れなくても、いいもの、納得できるものをつくる」という彼らの姿勢は私をある高みまで引っぱっていってくれた。とにかく一生懸命で責任感の強い小田からは徹底的に実社会のルールを教え込まれた。プロデューサーの手法も小田や鈴木から学んだ。
〈写真〉オフコース時代。1982年、大阪フェスティバルホールにて。
自分はドラマーという職人
ロックにこだわっていた私はオフコースに加わっても相変わらずロックドラマーだった。オフコースはレコードだけ聴いていれば「優しく、耳ざわりのいいバンド」だが、ライブではここぞとばかりドラムを叩いた。調子に乗って叩き過ぎ、メンバーに迷惑をかけたこともあったが、しっかりロックしていたと思う。ドラマーは決して前には出ないけれど、職人のようにドラムに徹するカッコ良さがある。この場合のカッコとは見た目のカッコ良さではない。生き方がカッコいいということだ。
私の言うロックとは心の底に「魂」を持ち続けている人たちの生き方の表現である。今は亡きビートルズのジョン・レノン、レッド・ツェッペリンのドラマー、ジョン・ボーナム。この二人は他に迎合することなく、自分の生き方を貫いた真の「ロッカー」だった。東北でいえば、イーハトーブの詩人あんべ光俊、秋田でいえば古武士のような風格の伊藤武三さん。秋田弁の劇作家伊藤さんは一本筋が通っていて小気味いいほどカッコいい。あんべは売れようが売れまいが、自分の歌を大切に唄いつづけている。
〈写真〉愛用のお宝スネアドラム。1957年ごろのものだという。
東京へのこだわりも消える
オフコースのシングル『さよなら』が大ヒットして念願の武道館公演も果たし、会館規模のコンサートを八百回以上も重ねたオフコースだったが、鈴木の脱退を契機に活動が減速。一九八九年二月、東京ドームでの解散コンサートを最後に四人はそれぞれの道に分かれ、私は一人のドラマー大間ジローになった。
精魂を傾けてきたバンドが役目を終えた時、十八歳の時から根拠地としていた東京へのこだわりも感じなくなっていた。そして、思い出されてくる故郷のこと。
四年前に母が亡くなって以来「ふるさとが懐かしい」そんな望郷の念が強くなっていた。ドラマーとして、プロデューサーとして、それまでどおりの活動をしながら、生活はのどかな故郷で、そんな風に考える年齢でもあった。妻も大館市生まれの秋田県出身である。一九九二年、二十年間暮らした東京を離れて家族とともに秋田市に移り住むことにした。
生活者としてかかわる
秋田県出身といっても、秋田は小坂町や高校時代を過ごした大館市しか知らない。市民になってみて、秋田市はコンパクトで好きな町だと感じている。山も海もすぐ近くにあり、森や林も豊かだ。しかし、通町などのように昔の家並みがつぶされて新しくなると「ふるさとの匂いが消えていく」ようで寂しい。秋田駅も新しくはなったが、駅に降り立ってもふるさとは感じられない。いわゆる箱もの的な街づくりはもう必要ないのでないかと思う。むしろ、地元の人たちに密着したイベントに興味がある。秋田で生活する者として地域にかかわっていきたいと思う。
ビートルズ・ボックス
来年の二月で一人のドラマー大間ジローになって十年になる。これまでを振り返ってみると、私らの世代に一番影響を与えたのはやはりビートルズ。財津和夫のチューリップやタケカワユキヒデのゴダイゴなど、ビートルズがいなければ誕生していなかったし、フォーク、ニューミュージック、ロックを超えて一つになれる、ビートルズはそういうルーツミュージックだ。このビートルズのナンバーをそのまま完全コピーに近い形でやろうと、私がまとめ役になって企画しているバンドがある。その名もビートルズ・ボックス。メンバーは松尾一彦、清水仁、そして私という元オフコースの三人と他にサポートメンバー四人を加えた七人編成のバンドだ。仕事があれば、メンバーの都合をつけて九州でも北海道でも、どこへでも集結しようという、そういう余裕のインターバルで楽しんでやりたいと思っている。
〈写真〉上 1996年8月、石川県加賀市で行われた「ビートルズ音楽祭'96」の野外ステージ。財津和夫、タケカワユキヒデ、白井貴子らと。左 憧れのビートルズのプロデューサージョージ・マーティン氏を囲んで…。
「よかったら聴いてみな」
現在、FM秋田の金曜日夜七時『J"S SOUND BOX』のプロデュースとDJをしているが、現代は付和雷同の時代で、リスナーのリクエストも「これが流行」といえば、そのサウンド一辺倒になってしまう。私が高校生のころはレッド・ツェッペリンやジェファーソン・エアプレーンをいち早く見つけて一人で悦に入っていたが、今の若い人にも自分の価値観でいい音楽を見つけてほしいと思う。でも、押しつけはしない。自分では七〇年代、八〇年代の和洋ポップ、ロックを語れるので「よかったら、聴いてみな」というつもりで、曲をかけている。そんな若い人に聴いてほしいのはやはり、ビートルズ。彼らの考え方、クリエイショナルなもの、録音技術など、あの時代のエッセンスが詰まっている。ビートルズからジョン・レノン、イーグルス、ドゥビー・ブラザーズにいってもいいが、一九六三年から七〇年代までのビートルズはぜひ体験してほしい。(談)(1998.11 Vol.16 掲載)
おおま・じろう
本名 大間 仁世(ひとせ)。
1954年、鹿角郡小坂町生まれ。大館鳳鳴高校卒業後、アマ、プロのロックバンドを経て1976年、オフコースにドラマーとして参加。1989年、オフコース解散。1992年から秋田市に在住。秋田を根拠地として県内外でミュージシャン、プロデューサーとして活躍中。