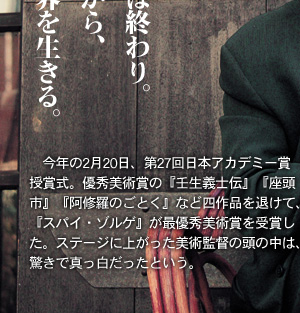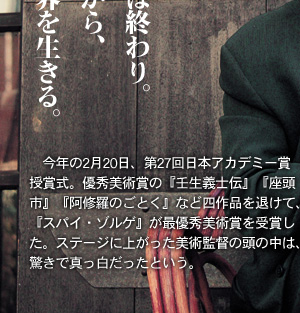|
「好きにやってくれ」
篠田 正浩監督は、美術監督にこう言った。映画『スパイ・ゾルゲ』のクライマックス。東京拘置所に収監されたリヒャルト・ゾルゲ(イアン・グレン)と尾崎
秀実(本木 雅弘)の取り調べのシーンだ。
史実では、取り調べを受けたのは十畳ほどの狭い部屋。しかし、及川はそこに、アールデコ調の重厚なセットを作り上げた。東京拘置所に教誨室があったことに発想を得て、拘置所に白壁の部屋を設け、中央に木彫のテーブルを置いた。ゾルゲが処刑前に静かな時を過ごした監獄にも、及川独自の美術を施した。篠田監督はこれを「独房のアールデコ」と、高く評価したという。
特撮の技術で起用
映画『スパイ・ゾルゲ』は、第二次世界大戦に突入する一九三〇年代の日本が舞台。ソ連の国際スパイであるリヒャルト・ゾルゲ(一八九五│一九四四)という実在の人物を主人公に、篠田監督が構想十年、製作費二十億円を投入して完成させた大作だ。監督人生の集大成として、ひとりの魅力あるスパイが動き回った大戦前の“昭和”をスクリーンによみがえらせた。
「舞台になった昭和初期という時代を、セットにするのは難しかった」と話す。実際にその時代を生き、風景を見た人々がいるからだ。しかしその難しさこそが、美術監督に思わぬチャンスを呼んだ。
「第二次世界大戦前の昭和は、知っている人もいれば現存するロケーションもあるリアルな風景。だから、CGを多用して、銀座の街並みを鮮やかに再現しなければならなかった。自分が起用された一番の理由は、CGの製作過程において、合成などの特撮技術における美術のノウハウを持っていたこと。その強みがあって、巨匠と初めて出会えた。特撮技術は映画『ガメラ』で鍛えられましたからね」。映画『ガメラ』の三作品はいずれも及川が美術監督を務めている。特撮技術を駆使した映画での評価が、思いがけず、篠田監督最後の映画への起用につながった。
ジャズを志して上京
 子どものころは秋田市の川反に住まいがあり、三味線のけいこ場によく出入りしていた。板塀が続く平屋の町並みには風情があり、格式があった。小路に入れば、狭い場所に小さな商いが軒を連ねていた。 子どものころは秋田市の川反に住まいがあり、三味線のけいこ場によく出入りしていた。板塀が続く平屋の町並みには風情があり、格式があった。小路に入れば、狭い場所に小さな商いが軒を連ねていた。
「今の仕事に生かされているとは思わないけれど、あのころの川反の雰囲気は忘れない。情緒ある町で、三味線の音色を聴きながら育ちましたよ」
中学ではブラスバンド部だったが、「つまらなくなってきたころ」に偶然ジャズと出合う。これまで聴いていた音楽とは明らかに違う曲、違うリズム…。いつの間にか、当時、秋田駅前の仲小路にあった「ロンド」に行くのが日課になっていた。
「今思えば、三味線もジャズも五音階だから、どこか似ていたのかもしれない。『ロンド』という異空間でサラリーマンではない生活のありようを見て、好きなジャズで生活していければいいと思った。テナーサックスを吹いて生きていければと思っていた」
そして高校卒業後、美術系の専門学校に通うことを、家族への“隠れみの”にして上京する。
平面と立体の魔力
映画美術との出合いは、サックスを吹いて音楽で生きていくことを夢見ていた専門学校時代。アルバイトでセットの絵を描いたのがきっかけだ。一枚の絵が立体的なセットに姿を変え、映像になっていく過程に言い知れぬ楽しさを感じたという。
「自分で描いた平面が、大道具さんの手に渡って立体になり、そこに役者が入って演技をして、撮影されて映画になる。二次元から三次元になって、またスクリーンという二次元に戻ってくる。それを『なんておもしろいんだろう』と思ったのが運の尽きで、映画の魔力に取りつかれた。麻薬みたいなものですよ」
 自分は音楽では食っていけない─。そう思い知ったことも、美術の道へと導いた。美術の助手は、時代劇セットの廊下磨きなどの下働きに励みながら、徐々に図面を描くチャンスを与えられていく仕事。図面描きと現場での経験を少しずつ積み重ねていく。「映画は封建的な世界。今はそんなことはないが、昔はけんかが日常茶飯事で、まるでヤクザの世界かと思ったほど」と振り返る映画の世界のたたき上げだ。 自分は音楽では食っていけない─。そう思い知ったことも、美術の道へと導いた。美術の助手は、時代劇セットの廊下磨きなどの下働きに励みながら、徐々に図面を描くチャンスを与えられていく仕事。図面描きと現場での経験を少しずつ積み重ねていく。「映画は封建的な世界。今はそんなことはないが、昔はけんかが日常茶飯事で、まるでヤクザの世界かと思ったほど」と振り返る映画の世界のたたき上げだ。
「美術というと金づちを持って走り回るイメージがあるが、実際は机にかじりついてひたすら図面を描く日々。『こういうのをやりたい』などと言っても、企画が起こらなければ予算は立たず、オファーもこないからただ待つだけ。その時々の予算に合わせて、どう美術を作っていくか。いい作品にたまたま巡りあえるかどうか、なんですよ」
一九八四年には助手から美術監督へ、八八年には『バカヤロー!』に起用される。この作品で本格的に一本立ちするまで、映画の道に入ってから十年以上の月日が流れていた。
その後は、『ガメラ』『学校の怪談』『川の流れのように』『カルテット』『プラトニック・セックス』などの映画やCMなどに関わった。しかし日本アカデミー賞受賞の前は、報われない思いから、秋田に帰ることを考えたほど落ち込んでいた時期もあったという。
「映画は“ばくち”みたいなものだから、内容が良くてもヒットには結びつかない。いい作品、いい本に巡りあえるように、日々をこなしていくんです」
監督の世界観を形に
 美術監督は映像のすべてに関わり、撮影現場のすべての土台を作る仕事だ。 美術監督は映像のすべてに関わり、撮影現場のすべての土台を作る仕事だ。
「監督の頭の中にある絵に合わせて、そのイメージを“助けていく”のが美術監督の仕事。監督の世界観を形にしていく。台本を読んで、監督と話をして、場所を設定してロケハンし、セットを設計していく時に個性が出るんです。平面図を描く時は、『こういうセットで、役者がこう入って、こういう演技をして、こう撮影する』と、現場でのひとつひとつの動きを頭でシミュレートする。だから、図面には“念”のようなものが入っている。手描きの図面には、線の引き方や、消しゴムで消して黒くなった跡などに美術監督の悩んだ様子が現れて周囲を動かすことになる。自分がジタバタしないと、周りは動かないものですよ」
そうさりげなく話すが、セットに役者が入る時の緊張感は並大抵ではないようだ。「撮影の前日は、今でも緊張して寝つきが悪い」のだと明かす。特に『スパイ・ゾルゲ』に必要だった調査やセット数の多さは半端ではなかったという。
「セット数は通常の五倍ぐらいあり、描いても描いても図面は終わらなかった。ゾルゲの時代はまだ記憶に残っている世界だから、篠田監督のリアリズムに挑まなければならない。ゾルゲが住んでいた家の写真は三枚ぐらいしか残っておらず、資料もほとんどなかったから、当時の日本家屋と照らし合わせて、美術パートの人間を総動員して調べまくった。達磨大師の絵は本物、カメラは当時のものを探しました。セットで作り切れるものと、作れないものとがあり、失敗と成功はいつも紙一重。美術が失敗すれば、映画は終わりだから必死です。でも人間、必死になって頑張れば何かがついてくる。歯を食いしばって積み重ねていけば、それをだれかが見ていてくれる。そう思わせてくれたのが日本アカデミー賞でしたね」
拘置所の美術を追求
第二次世界大戦直前の日本で、日本とドイツの最高機密情報を盗み出し、約八年に渡ってモスクワに送り続けたスパイ、リヒャルト・ゾルゲ。ドイツの新聞記者を装い、東京のドイツ大使館に潜入するため、ナチスに入党してまで命がけで行った諜報活動は戦後になってから明らかにされた。
ゾルゲが東京拘置所で処刑されたのは、戦争が終幕を迎えつつあった一九四四年十一月七日。処刑台に向かう長い廊下を、及川は、柱と梁だけで表現した。梁は、ゆるやかなアーチ型。暗闇にライトを照らせば、アーチは幾重にも影を作る。冷たいようでいて、優しく包み込むように連続するアーチのなかを、ゾルゲはゆっくりと通り抜けていく。それは、無機質でありながら穏やかな「死」への回廊だ。アールデコ調に設計した取り調べ室と同様に、及川がどこまでも、監督の世界観を追求した結果の表現だった。
そのシーンが、幻のようにぼんやりと、心に残って離れない。
|