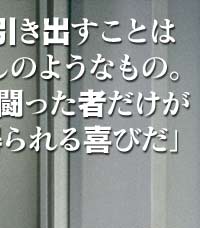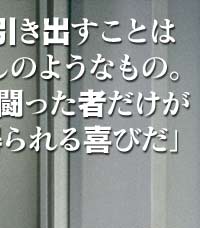|
 打たれて強くなる 打たれて強くなる
役者というより、長渕剛という人間があって、妥協しない強烈さがあった。必死に食いついても、蹴飛ばされそうになる。本当に苦しいと思った。「この人に負けないようなディレクターになりたい」と痛切に思ったものだ。そうやって苦しんだ甲斐があってドラマは大ヒットした。そして、長渕との出会いはそれまでの自分を変える転機になった。
その後、織田裕二という俳優に出会ったが、彼もクリエーティブな上に負けず嫌いの男だった。「これも何とか闘わなければ…」と、『お金がない』『振り返れば奴がいた』を制作した。彼らのような役者を相手に、常に闘いの場に置かれてきたから、少々のことには耐えられるようになった。仲間たちには我慢強いと言われるが、人間は打たれるほど強くなるものだと思う。そうした個性的な人たちと一緒に仕事をした作品が大ヒットしたから「もう一度こういう思いをしたい」と望むようになる。
 今が私の出発点 今が私の出発点
映画『ホワイトアウト』は織田裕二自身が監督を私にやってくれと指定してきた。私が秋田の雪国育ちだからよいと思ったのかもしれないが、真冬の山奥で4カ月間ロケをしたが、それはもう寒くてきつい仕事だった。しかし、映画の興行は大成功だったのでよかった。昨年は『ホワイトアウト』に続いて、テレビドラマ『やまとなでしこ』が成功して、ようやくここまで来れた!と実感している。ここまで、というのは「第三者が認めてくれるところ」までということだ。ここまで来た今が私の出発点だと思っている。自分の考えている作品を世に問うことができるまでになった。だから、やりたいことが以前より増えた。
本当は人見知り
この世界に入って、25年以上になるが、いまだに芸能人と話をするのは苦手だ。初対面の人は極度に緊張するし、あがってしまい、自己紹介さえも自然に話せない。学生の頃は華やかさに憧れていたけど、間近に芸能人に接すると恥ずかしくて…。根に都会コンプレックスがあって、東京生まれ東京育ちの人に気遅れしてしまう。パーティーなども慣れてはきたが、自分はこんな華やかな世界には合わないと実感している。人見知りで、見られることに緊張感を覚える。しかし、仕事に入ると、そんな人目などは気にしていられない。恥ずかしさよりも「ドラマをつくりたい」という欲求の方が強いからやって来られたと思う。
学生時代はテレビの仕事は華やかだし、スマートに仕事ができるだろうと思っていたが、実は大変な肉体労働だった。へとへとになるほど体力を使うし、華やかなイメージとのギャップがすごくある。
 宝を探す楽しさ 宝を探す楽しさ
闘って苦労して、そしてドラマが完成したら、視聴者の評価を受け、その時、自分もディレクターとして何を得たかがわかる。
『やまとなでしこ』では松嶋菜々子のこれまで隠れていた部分が引き出せたと思う。そういう未発掘の俳優・女優がたくさんいるような気がする。例えば、中山美穂は悪女の役や『花嫁の父』の花嫁役をやらせてみたらどうだろうか。彼女のこれまでのイメージを覆す部分を持っているような気がする。役者の未知の部分を引き出すことは監督としての醍醐味だろう。これは宝探しのようなものだ。
監督として誰もが起用したい俳優といえば高倉健だろう。未知の才能との出合いは監督としても新たな闘いになる。長渕、織田…この人たちによって鍛えられて自分も変わったし、掘り起こされたと思う。織田祐二に勝る役者が出てくればいいなぁ、なんて思っている。
「心の豊かさ」テーマに
新しいチャレンジとしてやってみたいのは老人を主人公にした映画。現代の70歳は昔と違って、老人とはいえないほど若々しい。それを社会は老人扱いして無理矢理老人にしている。70歳といっても、体力的にも精神的にも余力があるし、まだまだ社会は彼らを活用できるし、活用価値がある。会社でも、家庭でも、心にゆとりのある老人を活かそうよという、若者と老人のつながりをコミカルに描いた映画をつくってみたい。ドラマづくりの中心に、私は「心の豊かさ」をテーマとして据えている。
 風にそよぐ稲穂 風にそよぐ稲穂
一昨年、カメラマンの沢田教一さんを主人公にしたドラマ『輝ける時』のロケでベトナムを訪れた時だった。ベトナム戦争当時、沢田さんは目の前に広がる田んぼを見て「この風景、弘前と似ている」と言ったという。彼は青森県弘前市の出身だった。春、夏、秋と、日がな一日見て育った生まれ故郷の風景だ。私も田んぼや稲穂を原風景として思い出す。6月の早苗の頃、勢いよく緑が伸びる暑い盛りの田んぼ、そして黄色に染まった秋の田んぼ…映像を撮る時はそういう原風景が頭に浮かぶ。
秋田には東京では感じられない空の青さがある。天が広い。東京は建物があって空が見えないが、秋田は広い空が見えるし、天も高くて大きい。自然の風や空気を感じて育ってよかったと思う。そういう、田舎で育った人は話をしていてもわかる。自然の風や空気を感じて育った人に接すると「この人は田舎の人だな」と読み取れる。変われないものを持っているからだ。
私も山菜の季節になって、ワラビなんか食卓に出てくると、もう嬉しくて。体が自然の季節感を覚えている。
ドラマをつくる感動
子どもの頃は野球少年だったから、秋田商業高校に進んだが、入学してすぐに、自分には野球の才能がないと自覚してしまった。ちょうどその頃、NHKの『虹の設計』というドラマが放映されていた。天草に橋を架ける建設業の男(佐田啓二主演)の話だったが、このドラマに感動して、こういうドラマをつくる側の人間になりたいと思った。そして、日大芸術学部放送学科に進学した。大学卒業後は両親の希望を受け入れて秋田のテレビ局に就職したが、どうしても「ドラマをつくりたい」という欲求を断ち難くて一週間で東京に戻ってしまった。両親には寂しい思いをさせてしまったが、でも、テレビドラマを何本も見せることができたのでよかったと思っている。
秋田での思い出といえば友達、そして先輩に尽きる。特に秋田商業高校時代の先輩にはいろいろ教わって、お世話にもなった。困った時にはいつもだれかが助けてくれて、人間関係ではいい思いをしていた。両親が亡くなってからは、ほとんど帰秋することもなくなったが、友達や先輩は財産だと思う。
 息ぬきはニューヨーク 息ぬきはニューヨーク
現在は秋にテレビ朝日系で放送予定の『反乱のボヤージュ』を撮り終えたところ。『反乱のボヤージュ』は東大駒場寮の廃寮問題を軸に渡哲也演ずる舎監と若い寮生らとの対立と交流を描いた大作だ。この仕事でも渡哲也という、人間としても俳優としても素晴らしい人材と知った。これも出会いがなければ生まれなかった感動だと思う。「ドラマをつくりたい」と初めて思った時から、ずっとまっすぐにその道を進んできて、夢を追いかけて来れたことは一番幸せなことだった。
仕事を離れて、プライベートの楽しみといえば、旅行とゴルフ。旅行は主に海外に出かけることにしている。ニューヨークは妻も大好きで、6回ほど行っている。街そのものが刺激的で絶えず変化している、エネルギーにあふれている街だ。ドラマ制作が一段落したら、この秋にもまた行きたいと思っている。
(文中の敬称は略させていただきました)
|